7月30日ツイキャスhttps://twitcasting.tv/kenfawcjp/movie/631595137
(ツイキャスの不調で途中で途切れてしましました。ご了承ください。)
わたしはわたし
6月は「創世記」をテーマに学び、7月は「律法」を見ていきました。
まず「わたしはわたし」の回で、ユダヤ教の「一神教」の性質について考えました。人間は模倣的な存在であり、自分の意志で何かをしているつもりでも、自分の願いや欲は周りの影響によって形成されていて、結局社会の要求に応えるようにできていることが多い、ということをこのシリーズの中でずっと言っています。そのような中で人間は「神々」を想像し、自分たちのあり方を投影してきました。だから神々には善と悪の二面性があり、暴力性もあり、争い合ったり殺し合ったりもします。
しかしユダヤ教の一神教は、そのような人間的な模倣的争いとは無縁で、そのすべての外・上にいる「神」という存在が初めて想定されました。勿論その「神」にも人間的な要素が投影されることは多々ありましたが、人間や他の神々と争うような存在ではなく、そのすべてを超越する存在として描かれるようになりました。これが、人間が模倣的欲望から来る暴力と破滅のスパイラルから脱出するための第一歩となったのです。
この神が求めるのは、他の神々ではなくその神ご自身のみを礼拝することです。十戒で「私の他に神々があってはならない」と命じ、また偶像を作ることも禁じます。人間がそれまで描いていたような神々同士の争いとは無縁の存在だからです。
欲しがるな
その次は、「欲しがるな」というタイトルで、第十の戒めを中心に取り上げ、「模倣」についてさらに深めました。「法」という概念そのものが、人間社会の中で模倣的欲望が争いへと繋がるという経験則から、その争いへの発展を止めるために生まれたものだと考えられます。法には必ず「禁忌」がありますが、共同体の中にいる人々が互いに欲しがり、争いの種になりそうなものに制限が設けられます。だから食や性に関連する禁忌が古代の社会には多いのです。
しかしモーセ律法の画期的なところは、「欲しがること」そのものを禁じていることです。勿論、他の律法と違って、目に見えるものではないですし、それを取り締まることもできません。でも、人間同士の争いの本質を、律法は見事に捉えているのです。
イエスもこれについて言及します。よく「情欲を抱いてはならない」と引用され、性的な思いを持つことを姦淫と同じだ、というレトリックに用いられるマタイ5章の箇所は、実は第十の戒めの引用なのです。イエスは「あなたがたの義が律法学者やパリサイ人の義にまさらなければ、天の御国に入れません」と言いました。これは、律法学者やパリサイ人にもまして律法を一字一句完璧に守らないといけない、ということではありません。律法学者やパリサイ人は、人にどう見えるか、表面的な部分で何が罪で何が罪でないかを細かく定めて人々に要求していた彼らと違い、イエスは律法の第十の戒めが示すように、罪の問題は「欲しがること」、つまり外には見えないし、それに伴う罰や贖いの供え物も何もない「罪」ではあるが、それこそが本当の罪の本質であり、そこをきちんと対処しないと罪の問題、人間の暴力の問題は解決できないし、そこから脱却して神の国に入ることはできない、と言っているのだと私は思います。
聖書の二つの声
最後には、「聖書の二つの声」として、供犠について取り上げました。レビ記にある「罪のための生贄」の本当の目的について掘り下げ、また生贄を捧げなさいと聖書の中で命じられているにも関わらず、預言者を中心に、生贄について非常に批判的なテキストもたくさんあることを見ていきました。特にエレミヤ7:22では「そんなこと一切命じていない」と明確に言って、生贄そのものを切り捨てています。しかし実はレビ記1:1-2でも「もし・・・捧げるときは」という仮定形になっていて、律法の書を書いた人たちの間でも、生贄は人間が古来からずっと当たり前のように行ってきたもので、神からの命令ではないとう認識があったのかもしれません。イエスも預言者たちを引用して、供犠を批判しました。
カインとアベルも、方舟から出てきたノアも、神から何も言われていないにも関わらず生贄を捧げています。古代の我々の祖先は、そのような神との関わり方しか知らず、その文化的状況に神が合わせて下さり、生贄の方法にも制限を設け、それを通して人間を新たな境地に導く、或いは神の国へと招いて下さっていると読むこともできます。
供犠について細々と規定を設けているレビ記(と出エジプト記、民数記の一部)に対して、供犠がほぼ出てこないのが申命記です。申命記では、今も敬虔なユダヤ教徒が日々唱える「シェマ」が6章に出てきます。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして神を愛せよ、という命令で、イエスも第一の戒めとして取り上げています。
全体として申命記は、神の掟を守り、神に従うという関係性において、神が祝福と繁栄を約束して下さっています。しかしそれに従わなければ呪いと破滅が待ち受けている、いわば条件的な契約と言えます。では、申命記はレビ記等の「供犠」の考え方を乗り越えた新たな神の真実なのでしょうか?そうとも言えません。申命記のような二元論的な考えは、イエスの考えとイコールではありません。
イエスは、父なる神が「悪い人にも良い人にも太陽を注ぎ、雨を降らせてくださる」と言ったのに代表されるように、神を人間の行いに左右される存在ではなく、常に憐れみと恵みに満ちたアバ父という存在として伝えました。勿論この神像もイスラエルの歴史の中でずっと啓示されてきたものです。人を聖い・聖くないなどで分けて差別すること自体、結局は「供犠的」な人間のあり方です。聖書はそれを肯定するテキストもあれば、否定するテキストもあります。
つまり、聖書には「供犠的なテキスト」と「非供犠的なテキスト」があると言えます。このシリーズの主張では、人間は供犠的な存在であり、それが人間を破滅の危機へと追い込んでいて、聖書はそこから救いの道を与えようとしています。つまり、前者の「供犠的」なテキストは、元々の人間の姿をそのまま描写した「人間的なテキスト」或いは「宗教のテキスト」と考えることができます。後者の「非供犠的テキスト」、そこから人間を「神の国」のあり方へと導く「啓示のテキスト」であり、神の本来のあり方に近いものを指し示しています。
聖書は、すべてが神の完全な基準なのではなく、人間の現状をあらわす「宗教」と、神のより良い世界への希望と導きをあらわす「啓示」が混在する書物なのです。それを読み分けることが、クリスチャンにとっての重要課題です。
トーラの成り立ち
これまでの3回のセッションをザっと振り返りましたが、ここで「トーラ」と呼ばれるものの成り立ちについて述べておきたいと思います。まず、「トーラ」(律法)と言っても、その文脈次第で何を指すかは変わってきます。モーセが具体的に与えた掟・禁令を纏めて言うこともあれば、ヘブル語聖書全体をを指すこともあります。最も一般的な使い方は、創世記・出エジプト記・レビ記・民数記:申命記の5つの書、つまり「モーセ五書」です。ただし、新約聖書の「ノモス」(「トーラ」のギリシャ語訳)は、一般的な概念としての「法」や「原理」に意味で使われていたり、またガラテヤ書やローマ書での使い方では、ユダヤ教徒のアイデンティティの中心となる割礼、安息日遵守、コシェル(ユダヤ教の食習慣)を指していると指摘している学者もいます。各文脈でどのように理解するかは注意が必要ですが、このシリーズでは特段の説明がない限り、「モーセ五書」を指すものとします。
では、モーセ五書、つまり「トーラ」は、どのようにしてできたのでしょうか?モーセが神から啓示を受けて全て聞いた通りに書いたのでしょうか?聖書にそのような記述はありませんが、伝承では長らくそのように言われていて、今でも少数ですがそのように信じているキリスト教徒やユダヤ教徒もいます。しかし学術の世界では、口頭伝承として長らく語り継がれたものや、短いエピソードとして書かれた物語がずっと後の時代に集められ、当時の宗教家たちの手による編集・編纂を経て、最終的に「トーラ」として出来上がったとされています。つまり、たくさんの異なる「資料」が集められているとされています。では、これらの「資料」について、どのように考えられているのでしょうか?
文書仮説(JEPD説)
一時期は、トーラがJ・E・P・Dと呼ばれる四つの資料群から成り立っていると考えられていました。Jは「ヤハウィスト(Yahwist)と呼ばれる著者たちが書いた部分をを指します。神の名を「YHWH」(和訳は「主」、発音は「ヤハウェ」と考えられているが厳密には定かではない)と呼んでいたグループです。Eは、ヤハウィストに対して、神の名を「エロヒーム」(Elohim)と呼んでいたエロヒスト(Elohist)たちが書いた部分を指します。Pは祭司資料(Priestly Source)を指し、神殿の様々な行事を担当していた祭司たちが書いた部分を指します。最後に、Dは申命記資料(Deuteronomist)で、申命記を編纂したグループを指します。
元々の定説では、創世記から出エジプト記、そして民数記の物語部分が元々JとEによって書かれ、それをレビ記を書いた祭司たち(P)が様々に手を加えて編纂し、最後に申命記を書いた人たちが他の四書を編纂にも手を加え、モーセ五書が完成したとされていました。しかし、より古いと考えられていたJ資料(紀元前9世紀ごろの王朝時代に遡ると考えられていた)のうち、想定されていた時代にまで遡るとは考えられない部分があり、また「E資料」と呼べる箇所が非常に少なく、単純にYHWHを使っているのがJ資料でElohimを使っているのがE資料だと二分化するのに無理があることが分かってきました。現代の文献でも、JやEやPやDなどに言及することはありますが、単純に4つの資料群から成っている、という考えは崩れています。
現代では、Dは他から独立した伝承として考えられ、残りの部分は祭司資料と非祭司資料(Preistly and non-Preistly Sources)に分けて考えられます。非祭司資料をJE資料と呼ぶ場合もあります。更に祭司資料も、従来のPだけでなく、H(Holiness; 神聖祭司、「神は聖である・・・」を繰り返すことが特徴)という別の祭司著者グループがいたこと考えられています。具体的な仮定については、これからも新しい説が出るかもしれませんが、要約すると、バラバラに存在した長短様々な伝承が、様々な編纂の過程を経て、紀元前5世紀ごろに「トーラ」として仕上がったようです。これが覆ることはおそらくないでしょう。
それぞれの神学
様々な異なった資料があるということは、その中に異なった考えも混在しているということです。「聖書は一貫した神の御心を示している」などと教会から教わったかもしれませんが、このシリーズではそのような考えは一旦捨てていただけたらと思います。人間についても、神についても、正しい行いや神を喜ばせ神の祝福を得る方法についても、異なった見解、時には矛盾するような考えが、敢えて一つの書に纏められているのです。私たちが気付く矛盾など、聖書を編纂し、それを毎日読んで暗記・暗証していたイスラエルの人々は、当然気付いています。でも、イスラエルは当たり障りのない、突っ込みどころのない物語だけを入れたのではなく、様々な伝承を自分たちの信仰の先達者たちから継承するものとして、省かずに混在させたのです。
また、編集者・編纂者たちは、ただ書いてあったものをそのまま聖書に含めただけでなく、自分たちで加筆・修正を多分に加えました。過去の人たちの知恵に頼りつつも、自分たちが生きた時代に相応しい物語へと柔軟に書き換えていったのです。これは、私たちが「聖書」そのものを自由に書き換えて良い、ということではありませんが、過去の人たちの知恵を参考にしつつも、それに縛られる必要はないということです。自分たちで自由にそれを活用し、自分たちの時代にあった方法で人々に語っていくべきだと思います。
今の時代には今の時代の神学が必要です。聖書のテキストから熱心に学びつつも、今の人たちを救いに導けるような神学を、共に築き上げていきたいと思います。
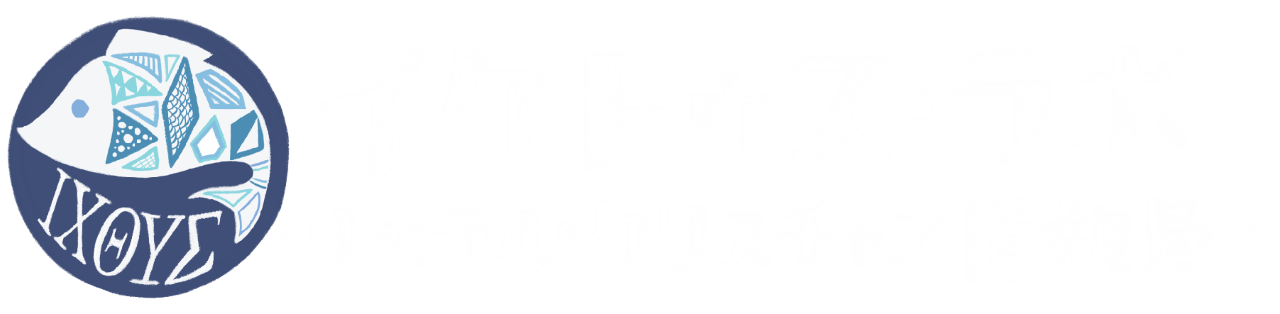
コメントを残す